Our work in Africa
Humane World for Animals tackles the root causes of animal cruelty and suffering to create permanent change. We make change at scale, advocating for policy change at all levels of government and working with companies so that they can be kinder to animals their businesses impact. We work in partnership with communities, bringing diverse expertise to the most complex issues, and doing it all with a compassionate and welcoming approach.
Our impact
We envision a world without animal cruelty, where humans and animals coexist peacefully. In Africa, we work to promote non-lethal solutions to human-wildlife conflicts, improve the lives of animals raised for food, end the illegal wildlife and captive big cat trade, advocate for a more plant-forward food system, increase access to spay/neuter services and primary veterinary care for companion animals, ending cosmetics animal testing and helping animals in disaster situations.
outside Kruger National Park have received an immunocontraceptive vaccine
have a permanent home at our sanctuary in Liberia
in South Africa have been sterilized through our Healthy Pets, Healthier Communities initiative
Latest News
「東京都、象牙取引見直し作業の再開を求められる」
ワシントンDC/東京(2020年6月26日) – ゾウの保護を求める国内外の諸団体は、本日、東京都に対し、小池百合子知事のリーダーシップのもと、着手済みの東京都内の象牙取引の評価をやり遂げることにより、都内における象牙取引の問題点を検証し、その対策を示すことを求める。これは、東京が「ニューノーマル」を覚悟し新型コロナウイルスに順応的に対応する中、ゾウを保護するために既に行っていた要望を再度行うものである。東京都は、4か月にわたって中断している「象牙取引規制に関する有識者会議」を速やかに再開されたい。 アフリカゾウが象牙目的で密猟され続けている一方、日本政府は合法化された象牙の国内取引を適切に規制することに失敗してきた。表面的な規制が抱える抜け穴は、違法取引を助長している。全形が保持された牙は、合法性を確認するための措置を実質的に欠いたまま、数十年間にわたって販売され続けた。日本では、未加工象牙の80%がハンコに加工されている。また、日本による象牙取引は、他国による取引禁止の実効性を弱め、国際取引上の問題も引き起こしている。2018年以来、日本から輸出された象牙が中国の現地当局によって押収されるケースが、 少なくとも65件確認されている。 ヤフー、楽天、イトーヨーカドーおよびイオンを含む日本の大手小売業者は、象牙の違法な国内取引および輸出に加担することのないよう、既にその販売を停止している。 2020年1月、東京都は、都内における象牙取引の現状およびそれに対する規制内容を検証し、その評価のもと東京都がなすべき対策を示すため、新しい委員会を設置することを発表した。「有識者会議」の8名の専門家は、同月に一度目の会合を持ったものの、それに続く会合と、当初5月と期待された政策の公表は、やむを得ず延期されている。同年3月30日、30の内外の環境保護団体および野生生物保護団体は、知事に対し、東京都の先進的な行動を称賛する 書簡を送っている。 「ヒューメイン・ソサエティー・インターナショナル」の野生生物プログラム上席専門員であるアイリス・ホは、次のように述べる。「世界中の政府が新型コロナウイルス蔓延に対する取組みに奔走している中、不幸なことに密猟は『ロックダウン』されず、密猟者はこの機を利用して、何の咎めもなく野生動物を殺し続けています。そのことは、つい最近、1日で6頭ものゾウが殺されたエチオピアの事件で裏付けられています。人類が自然との関係を見直すよう迫られる、新型コロナ後のグローバルな野生生物保護にとって、東京都による象牙の商業取引禁止は、まさに待望の積極的な流れをもたらすことになるでしょう。」 東京都に拠点を置くNGOである「トラ・ゾウ保護基金」の事務局長である坂元雅行は、次のように述べる。「これから私たちは『ニューノーマル』時代の新しい国際都市・東京で生き、活動することになります。それは、 国レベルで遅れをとるデジタル化の加速等によって都市の社会経済機能の強化と人々の安全な生活を同時に確保しつつ、グローバルスタンダードにしっかり向き合う都市であるはずです。ゾウの苦難と国際社会からの批判にもかかわらず、もっぱらハンコを作るために続けられてきた象牙取引に終止符を打つこと。それは、今だからこそいっそう、都民が歓迎することではないでしょうか。」 昨年、東京都における象牙市場を閉鎖しゾウを象牙取引から守るための取組みに参加するよう、 デブラシオ ニューヨーク市長が小池知事に直接呼びかけた。中国、米国、英国など世界の主要な象牙消費国は、既に国内象牙市場閉鎖のための措置をとっている。「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)第18回締約国会議において各国は、日本のように合法的な象牙市場を開いている国に対し、その市場が違法取引の一因になっていないと保証できるだけの措置(がとられているのかどうか)について報告させることに合意している(締切は今月)。 「環境調査エージェンシー(EIA)」の上級政策アナリストであるエイミー・ゼツ・クロークは、次のように述べる。「東京のゾウを保護するための先進的な努力は、日本国政府が、ゾウではなく象牙産業を守るという態度を取り続ける中、大いに歓迎できるものです。国際社会は、東京都が象牙取引を見直すという公約とその実行を最後まで成し遂げられることを待ちわびています。小池知事と東京都におかれては、都内における象牙販売をできる限り速やかに禁止する措置をとっていただくよう、お願いいたします。」 了 お問合せ先 : 坂元雅行, 認定NPO法人トラ・ゾウ保護基金, 03-35595-8088, yukisakamoto@jtef.jp Nancy Hwa, Humane Society International (U.S.), 202-596-0808 (cell), nhwa@humaneworld.org Lindsay Moran, Environmental Investigation Agency, lmoran@eia-global.org
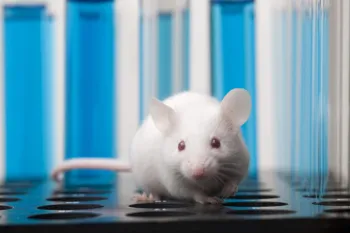
動物との共生を考える連絡会とヒューメイン・ソサイエティー・インターナショナルが動物実験のあり方を問う資料集を公表
東京—科学上の目的のために利用される動物に関する3Rの理念、動物実験の「代替(replacement)、削減(reduction)、苦痛の軽減(refinement)」が提唱されてから60周年に当たる今年、動物との共生を考える連絡会とヒューメイン・ソサイエティー・インターナショナル(Humane Society International, HSI)が、動物実験代替法の研究者や実験動物の専門家のなど、動物実験の課題に関する様々な関係者が執筆した記事を収載した新たな資料集『資料集:動物実験のあり方を考える』を公表した。 動物との共生を考える連絡会とHSIは、今年成立した動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護法)の改正に向けて、所轄省庁や国会議員に対して共同で働きかけを行っていた。改正動物愛護法には、附則において実験動物について引き続き検討する旨が含まれ、動物との共生を考える連絡会とHSIは、今回の改正後も引き続き、関係者に対して働きかけを行い、社会の啓発を行うために共同作業を進めている。 資料集には、アメリカやヨーロッパを始め、世界各国における動物実験に代わる動物を用いない研究・試験方法などを促進・義務化するための法令や政策について包括的な解説を提供する記事も含まれる。このような政策上の取り組みに共通するテーマとして、代替法の利用の義務化(3Rを法令に組み込む)、科学的に不必要であるとみなされる動物の利用の禁止(例えば、化粧品の動物実験など)、そして動物の利用の代替と削減を達成するための指標やタイムテーブルの立案などが世界的動向として見られることが指摘されている。 動物との共生を考える連絡会の青木貢一代表は次のように述べている。「本資料集は、世界各国の規制の状況や、動物実験や実験動物の関係者のそれぞれの状況や立場を概観するものです。先の動物愛護法改正において、実験動物について検討を続ける旨が附則に含まれましたが、様々な角度からの現状に関する情報をまとめたこの資料集が、すべての利害関係者が参画できる健全な対話のきっかけになればと願っております。」 HSI研究毒性学部門副部長のトロイ・サイドルは次のように述べている。「世界中の多くの国が、動物実験にかかわる規制や、動物を用いない最新の科学技術の取り入れを促進するための法令を設けており、この資料集により、このような世界的動向に関して日本の関係者の皆様に最新の情報を提供できればと思っております。このような規制の動向の一例が、化粧品業界に起こっている変革です。現在、既に39の市場で化粧品の動物実験の実施や動物実験された化粧品の商取引が禁止され、アメリカやカナダをはじめとしたその他複数の国でも同様の法案が検討されています。これらの規制は、ヒト生物学を基盤とした動物を用いない代替法に移行する原動力となっているのです。日本の関係者にはぜひこの資料集を、改正動物愛護法の附則にかかわる今後の議論の糧にしていただければと願っております。」 資料集は、今後随時関係者に直接手渡される予定であるが、一般の方も無料で こちらから全文をダウンロードすることができる。 以上 問い合わせ : HSI (日本): 山﨑佐季子, syamazaki@humaneworld.org (日本語・英語対応可) 動物との共生を考える連絡会: 青木貢一 info@dokyoren.com ヒューメイン・ソサイエティー・インターナショナル(Humane Society International, HSI) 及びそのパートナー団体は、世界最大級の動物保護団体です。HSI は 25 年以上にわたり、科学、アドボカシ―、教育及び実践プログラムを通して全ての動物の保護に取り組んできました。「世界中の動物に畏敬の念を示し、動物虐待に立ち向かう」ウェブサイ ト― hsi.org/ 動物との共生を考える連絡会は、「人と動物が共に幸せに暮らせる社会づくりを目指す」という趣旨に賛同した団体・法人・個人の連合体であり、「動物の愛護および管理に関する法律」を国民に周知し、同時にこの法律をより良いものに改正するために、管轄官庁や行政自治体、国会議員などへのロビー活動などを行う連合体です。ウェブサイト – https://www.dokyoren.com/
ビル・デブラシオ ニューヨーク市長が、小池百合子 東京都知事へ 日本における象牙取引禁止に対する支持を要請 動物保護団体および環境保護団体から称賛の声が上がる
仮訳 プレスリリース ワシントン(2019年5月17日)-ビル・デブラシオ ニューヨーク市長が、小池百合子 東京都知事に対し、世界最大の象牙市場を擁する日本で象牙取引を終焉させる取組みを支持するよう要請した。影響力を高めつつある世界のリーダー・市民選出の公職者の一人に数えられるデブラシオ市長が、とりわけ2020年夏の競技大会の開催が迫るこの時期に、全ての象牙販売を禁止し、違法な象牙取引を撲滅することを求めているのである。 デブラシオ市長は、 小池知事に送った手紙の中で、次のように述べている。 「翌年の五輪の主要テーマは、『持続可能性』とされ、これが『より良い未来へ、ともに進もう。』というコンセプトによって、五輪の行動規範に反映されています。」「数百万の人々が東京を来訪するに際し、厳格な象牙規制のある国々からも、多数の来日があります。これらの旅行者と競技参加者は、自国へ持ち帰るお土産にしようと、それとは知らずに日本の法令に違反して象牙の違法取引に手を染めてしまうかもしれません。そうなれば、無用な苦痛を味わい、自らのオリンピック体験に傷をつける結果となるのです。」 ニューヨーク市と東京都は、この数十年、経済面および文化面で緊密な関係を築き上げてきた。ニューヨーク州は、象牙製品の販売を禁止している米国の9つの州のひとつでもある。ニューヨーク市は、広く知られているとおり、2015年にタイムズ・スクエアで、2017年にセントラル・パークで、押収象牙の粉砕処分を行った。一方の日本では、中国が象牙取引を禁止した2018年の後に世界最大となった象牙市場が維持されており、両者は対照をなしている。 ヒューメイン・ソサエティー・インターナショナルの野生生物プログラム上席専門員であるアイリス・ホは、次のように述べる。「2020年五輪は、日本にとって世界の舞台で、自らが名声を博しつつ責任を伴ったリーダーであることを示す重要な機会となります。象牙取引が禁止されないままに夏の競技大会が開催されれば、数百万人の旅行者に、持出し違法な象牙土産に手を出す機会を与え、国境を越えた象牙の違法取引という惨事を招くことになるでしょう。我々は、象牙取引よりもゾウの存続を選択することで、『より良い未来へ、ともに進もう』とすることができるのです。」 ヒューメイン・ソサエティー・米国のニューヨーク州部長であるブライアン・シャピロもまた、象牙の違法取引に対してゾウをより万全に保護しようとする、この取組みを称賛する。 トラ・ゾウ保護基金の事務局長である坂元雅行は、次のように述べる。「日本では象牙の80%がハンコを大量生産するために消費されます。しかし、象牙は決して伝統的な印材ではありません。生きたゾウを守るためとあれば、東京都民が、象牙の販売禁止にもろ手を挙げて賛成することに疑問の余地はありません。」 環境調査エージェンシー(EIA)の上級政策アナリストであるエイミー・ゼツ・クロークは、次のように述べる。「日本の象牙取引は、米国、中国その他の国における象牙需要を刺激し、そこで実施されている国内象牙取引禁止の効果を削ぐおそれがあります。アフリカゾウ保護に対する責任を真に果たすためには、2020年に東京で開催される競技大会に数百万人のアスリートと観客が来日する前に、日本は国内象牙市場を閉鎖しなければなりません。」 デブラシオ市長からの書簡に加え、5月7日には、37名の米国下院議員が、杉山晋輔 在米国特命全権大使に対し、存続の危機にあるゾウを保全するために、日本が世界の国内象牙市場を閉鎖する取組みに加わるよう求める 書簡を送っている。この書簡は、マデリーン・ディーン議員(ペンシルベニア州、民主党)、ピーター・キング議員(ニューヨーク州、共和党)を中心に取りまとめられ、賛同者には下院外務委員会議長のエリオット・エンゲル議員(ニューヨーク州、民主党)も含まれている。 背景事実 日本には、公式に発表されている数としては世界最大となる、計1万6000以上の象牙製造業者、卸売業者、小売業者が存在する。 2011年から2016年にかけて、日本から中国へ輸出された2トン以上の象牙が、中国当局によって押収されている。 日本の象牙市場は、国境を越えた違法な象牙取引を促進し、中国による法執行の効果を削いでいる。 アフリカゾウの生息国を含むアフリカ32か国から成る「アフリカゾウ連合」は、日本に対し、国内象牙市場を閉鎖するよう訴えている。 多数の国および地域、例えば米国、英国、フランス、ルクセンブルグ、ベルギー、中国、香港、台湾などが、国内象牙取引の禁止または規制を、宣言または実施している。 * 象牙取引およびゾウの写真について リリースの電子ファイル(英語版のみ)には、写真ライブラリへのリンクが張られています。ご希望の方は、「ご連絡先」のいずれかへ、e-mailにてご連絡ください。 ご連絡先 Humane Society of the United States: Rodi Rosensweig, 203-270-8929, RRosensweig@humaneworld.org Humane Society International: Nancy Hwa, 202-676-2337
ユニリーバがヒューメイン・ソサイエティー・インターナショナルの化粧品の動物実験を世界的に終わらせる取り組みへの支持を表明
ロンドン—パーソナルケア製品の大手企業であるユニリーバが、世界中の化粧品の動物実験を5年以内に終わらせることを目標としたヒューメイン・ソサイエティー・インターナショナル(HSI)の#BeCrueltyFreeキャンペーンを支持することを表明した。ユニリーバの支持には、消費者の安全性の評価における、現代的な動物を用いないアプローチの規制への受け入れを促進することを目的とした新たな壮大な協働体制の構築も含まれる。 Dove、DegreeやTRESemméなどの人気のブランドで知られるユニリーバは、世界で2番目の規模を誇る美容製品会社で、業界のトップ10の中で化粧品の動物実験を禁止するための規制改革を積極的に支持する企業としては初となる。関係者らは、この新たな協働体制が、世界中の化粧品業界における規制の変革の促進につながり、2023年までに世界中の50の主要な化粧品市場において動物実験を禁止するという共有された目標を達成できることを期待している。 HSI研究毒性学部門副部長のトロイ・サイドルは次のように述べている。「どの企業でも化粧品における動物実験代替法を支持すると言うでしょう。しかし、ユニリーバは、化粧品の動物実験そのものを禁止することを全面的に支持してくださった最初の化粧品業界の大手企業となりました。世界各国で、毎年何十万匹もの動物がいまだに化粧品の毒性試験のために使われている中、この動物たちにとって残酷な状況に、未来永劫終止符を打つために、HSIと共に立ち上がってくださったユニリーバに称賛の意を表したいと思います。この例に続き、美容業界の他の大手企業にも、ぜひ私たちと共に立ち上がってほしいと願っております。」 新たな協働体制には次の事項が含まれる: 欧州連合(EU)において確立された前例と同様、当該国内における化粧品の動物実験の実施及び禁止施行以降に新たに動物実験された化粧品の販売の禁止が盛り込まれた規制を実現するための、HSIとそのパートナー団体による取り組みへのユニリーバの支持。 企業や規制当局が動物を用いないアプローチのみに頼った化粧品の安全性の担保ができるようにするための技能の開発のための、数年間にわたるオープンな協力体制の開始。 長期的な技術の蓄積のために、安全性を担う将来の科学者たちにおける動物を用いない「次世代」リスク評価の訓練への投資。 ユニリーバの主任研究開発オフィサー(Chief Research and Development Officer)のDavid Blanchardは、次のように述べている。 「化粧品の動物実験の時代を終わらせるために、ヒューメイン・ソサイエティー・インターナショナルと協働体制を構築できたことをうれしく思います。他の企業、規制当局やその他関心のある関係者の、この重要なイニシアチブへの参加もぜひ歓迎します。」 世界中で、37か国において化粧品の動物実験を完全または部分的に禁止する法律が施行されている。HSIは、2013年に欧州連合(EU)における禁止の最終段階の施行を促す際や、それに続いたインド、台湾、ニュージーランド、韓国、グアテマラやブラジルにおける7つの州において禁止を実現するにあたって、カギとなる役割を果たした。現在、HSIとそのパートナー団体は、オーストラリア、ブラジル、カナダ、チリ、メキシコ、フィリピン、南アフリカ、スリランカ、ベトナム及びアメリカにおける10か国の規制を変革するために取り組みを進めている。 化粧品業界において実施されている動物実験には、化粧品やその原料が毛を剃ったウサギの皮膚に塗布されたりや目に点眼される皮膚刺激性試験や眼刺激性試験、モルモットやマウスを使った皮膚アレルギー試験、そして何か月間も実施される強制経口投与による試験などがある。これらの試験は動物に重篤な痛みや負荷を与え、失明、目の腫れ、皮膚のただれや出血、内出血、臓器の損傷、けいれんなどを引き起こし、動物が死に至る場合もある。鎮痛剤が与えられることは少なく、試験後に動物は、窒息、断頭や首の骨を折るなどして殺処分される。 ユニリーバの動物実験代替法に関する意見表明(2018年10月)は、下記のリンクより閲覧することができる。 https://www.unilever.com/Images/animal-testing-position-statement_tcm244-526667_en.pdf # 問い合わせ: HSI (日本): 山﨑佐季子, syamazaki@humaneworld.org (日本語・英語対応可) HSI (イギリス・グローバル): Wendy Higgins, +44 (0)7989 972 423, whiggins@humaneworld.org HSI (アメリカ): Nancy Hwa, 202-676-2337 (オフィス), 202-596-0808 (携帯)
動物との共生を考える連絡会とヒューメイン・ソサイエティー・インターナショナルがすべての動物をより確実に守る法律に向けた市民フォーラムを開催
動物との共生を考える連絡会とヒューメイン・ソサイエティー・インターナショナル(Humane Society International, HSI)が、動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護法)の改正の機運を高めるために市民フォーラムを開催した。フォーラムでは、動物愛護法を、愛護精神を推進するための理念法として捉えるのではなく、より具体性を持った動物を守る手段となる部分を強化する必要性が語られた。そのためにはどの様な課題があるかなどに関する議論が展開された。また、実験動物や畜産動物など、ペット以外の動物に関する動向と課題について取り上げ、2020年の東京オリンピックに向けて、あらゆる動物を守る具体的な法律として機能するような動物愛護法の必要性が提言された。 動物との共生を考える連絡会とHSIは、動物愛護法改正に向けて、所轄省庁や国会議員に対して共同で働きかけを行うと同時に一般社会の全体的な意識の向上に努めており、フォーラムはその一環として開催された。 当日は、動物保護団体の関係者をはじめ、動物愛護法改正に関心のある多くの市民が参加し、50名ほどの参加者で会場がにぎわった。 動物愛護法改正に向けて、この法律は、人間の財産を守り愛護精神を社会に根付かせるためのものであり、動物を守るための法律ではないという議論が出てきており、この解釈が根付いてしまうと、日本は先進国の中、唯一動物を保護する法律がない国ということになってしまう。このような中、本フォーラムでは、動物愛護法が具体的に動物を守れるような法律として機能するためには何が必要か、現行法の課題について法律の専門家である浅野明子弁護士が解説した。 またフォーラムでは、畜産動物と実験動物に関するそれぞれの課題が取り上げられた。実験動物については、近年動物実験から動物を用いない最新の代替法への移行が進められており、本フォーラムでは代替法の最新動向について取り上げた。ヒト生物学を基盤とした代替法に移行することは、犠牲になる実験動物を減らすことができるだけではなく、よりヒトへの安全性が高い商品開発につながるのである。動物との共生を考える連絡会とHSIは、日本の実験施設における動物の境遇を改善するため、動物愛護法の実験動物にかかわる条項の強化に向けて協力体制を築いている。 畜産動物についても、動物の福祉を保障した生産体制について日本における取り組みが紹介された。畜産動物の福祉を向上させることも、動物のためだけではなく、公衆衛生、食品の安心・安全及び畜産の経済にとってもプラスとなり、人間の生活の質の向上につながる。 動物との共生を考える連絡会の青木貢一代表は次のように述べている。「動物愛護法改正の法案がもうすぐ提出される見通しですが、この改正によって、法律があらゆる動物を守るための具体性をもった内容に少しでも舵を切ることができることを願っています。このフォーラムが、改正に向けた一般市民の意識向上と機運醸成に貢献できたことを期待します。」 HSI研究毒性学部門副部長のトロイ・サイドルは次のように述べている。「世界中、多くの国が、動物を守ることを目的とした包括的な動物福祉の規制を設けており、動物愛護法が最初に制定された時期から、世界各国の動物福祉の規制には大きな進展がありました。例えば、実験動物ひとつとっても、現在37の市場で化粧品の動物実験の実施や動物実験された化粧品の商取引が禁止され、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ブラジル、チリ、スリランカや南アフリカなどでもこのような法案が検討されています。これらの規制は、ヒト生物学を基盤とした動物を用いない代替法に移行する原動力となっているのです。日本の当局もこのような世界の規制の流れに乗ってくださることを期待します。」 以上 問い合わせ: HSI (日本): 山﨑佐季子, syamazaki@humaneworld.org (日本語・英語対応可) 動物との共生を考える連絡会: 青木貢一 info.dokyoren@gmail.com ヒューメイン・ソサイエティー・インターナショナル(Humane Society International, HSI) 及びそのパートナー団体は、世界最大級の動物保護団体です。HSI は 25 年以上にわたり、科学、アドボカシ―、教育及び実践プログラムを通して全ての動物の保護に取り組んできました。「世界中の動物に畏敬の念を示し、動物虐待に立ち向かう」ウェブサイ ト― hsi.org/ 動物との共生を考える連絡会は、「人と動物が共に幸せに暮らせる社会づくりを目指す」という趣旨に賛同した団体・法人・個人の連合体であり、「動物の愛護および管理に関する法律」を国民に周知し、同時にこの法律をより良いものに改正するために、管轄官庁や行政自治体、国会議員などへのロビー活動などを行う連合体です。ウェブサイト – https://www.dokyoren.com/
研究により農薬評価への貢献がないことが判明したのち、日本が、農薬におけるビーグル犬を用いた1年間の毒性試験の要件を廃止
東京・ソウル(2018年04月02日)— ヒューメイン・ソサイエティー・インターナショナル(Humane Society International, HSI)は、除草剤等の農薬におけるビーグル犬を用いた1年間の毒性試験の要件を廃止するという日本の農林水産省の決断を歓迎する。この試験では、32頭ものイヌが、1年間毎日、農薬を混ぜた食餌を与えられる。その後、イヌは処分され、内臓の状態が観察される。これは、何千匹もの動物が使われる一連の農薬の毒性試験の一部に過ぎない。 農林水産省の決断は、2年間に及んだ食品安全委員会委託の研究に基づいたもので、研究においては、イヌを用いた1年間の試験が、人間における安全な暴露レベルを定める際に価値のある情報をほぼ貢献しておらず、したがってほとんどのケースにおいて試験を実施する必要がないことが示された。この研究結果は、2007年にアメリカにおいて始まり、そしてその後インド、欧州連合、ブラジル及びカナダと続いた規制要件の改正につながった過去に実施された類似の分析研究と一致した結果であった。HSIは、これらの規制改正のための交渉の多くの最前線で、グローバルなネットワークや各国で運営されている事務局及びプログラムを駆使して取り組みを展開させていた。 HSI副会長兼研究毒性学部門の担当のトロイ・サイドルは次の通り述べている。 「農薬のデータ要件から、この不必要かつ非人道的な試験を廃止するという日本の決断を称えると同時に、説得力のある科学的根拠が既に存在するにもかかわらず、国によっては行動を起こすまでに20年近くもかかっているということが残念でなりません。動物実験の廃止に向けた科学的な根拠が確立され次第、すべての国が即座に廃止に向けて動くようになるよう、農薬のデータ要件やリスク評価のアプローチについて、今よりももっと質の高くかつスピーディーな国際調和が急務であると考えます。各国の動きが遅いという理由のみで、犬たちが20年もの間、不必要に苦しみ続けるということは、決して許されるべきではありません。」 韓国、台湾やアルゼンチンは、引き続き1年間のイヌの試験を農薬の要件としている。この状況は、国際的な規制調和や、動物実験の要件を廃止する取り組みにおける協力体制の強化の必要性を浮き彫りにしている。HSIは、動物を用いないアプローチの開発、情報の共有、データの相互受理、そして重複する研究の回避に関するグローバルな取り組みに、すべての国の完全な参加を奨励するために活動している。 1年間のイヌの試験について: ほとんどの国の規制要件において、 農薬の「有効成分」(農薬の効果をもたらす毒物)一件を登録するために、最大10,000匹のげっ歯類、魚類、鳥類、ウサギ及びイヌが、何十通りもの化学物質の毒性試験において用いられる。これらの試験の多くは重複しており、2種類以上の動物や異なる暴露の経路(経口、吸入、経皮等)における反復となっており、科学的な価値の厳しい再評価を求める声が挙がっている。 委託研究においては、286件の農薬の評価が分析され、95%近くにおいて、人間にとっての安全な暴露量を定める際に、1年間のイヌの試験が重要な知見を貢献することがなかったことが示されている。この結論は、日本において登録された45件の農薬における1年間のイヌの試験のデータを分析した、独立した研究者らが公表した先行研究と一致している。(Critical Reviews in Toxicology, volume 44/issue 10, 2014において公表されたWerner Kobelら著 “Relevance of the 1-year dog study in assessing human health risks for registration of pesticides. An update to include pesticides registered
動物との共生を考える連絡会とヒューメイン・ソサイエティー・インターナショナルが動物愛護法改正に向けて、市民フォーラムを開催
istock 東京 — 2月12日(月祝)、動物との共生を考える連絡会とヒューメイン・ソサイエティー・インターナショナル(Humane Society International, HSI)が、動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護法)の次回の改正に向けて市民フォーラムを開催した。フォーラムでは、実験動物、農業動物、展示動物等、あらゆる動物の福祉の動向と課題について取り上げ、2020年の東京オリンピックに向けて、「動物愛護」から、より科学的な視点でかつ動物保護関連法の国際基準となっている「動物福祉」への転換が提言された。 動物との共生を考える連絡会とHSIは、日本の実験施設における動物の境遇を改善するため、動物愛護法の実験動物にかかわる条項の強化に向けて協力体制を築き、所轄省庁や国会議員に対して共同で働きかけを行うと同時に一般社会の意識の向上に努めており、フォーラムはその一環として開催された。 動物福祉とは、客観的な評価や研究から成る、科学的な概念であり、動物の生活の質に焦点を当てた比較的新しい学問である(1980年代に、EUにおいて農業動物の福祉について検討するための資料が多く作成された)。フォーラムでは、犬猫等のペットをはじめ、実験動物、農業動物、展示動物等が、動物福祉を根幹とした法令によりどのように扱われているか、科学的視点からの議論が展開された。参加者は、海外の動物福祉の専門家でありHumane Society of the United States (HSUS)の最高科学責任者であるアンドリュー・ローワン博士による世界各国の動物福祉の最新動向についての講演に、熱心に耳を傾けた。 また、世界各国の動物福祉の動きは、動物への配慮という枠を超え、人間の生活の質の向上にもつながることを示す事例も多々挙げられた。例えば、現在、世界において37か国が化粧品の動物実験を禁止するに至っているが、このような動きは犠牲になる動物を減らすことができるという動物福祉の観点だけではなく、これらの禁止は、化粧品企業にヒト生物学を基盤とした動物を用いない代替法に移行することを法的に義務付けることによって、よりヒトへの安全性が高い商品開発につながるのである。また、農業動物の福祉を向上させることも、動物のためだけではなく、公衆衛生、食品の質及び畜産の経済にとってもプラスとなる。 動物との共生を考える連絡会の青木貢一代表は次のように述べている。「今年は動物愛護法の改正に向けて様々な関係者が動いていますが、法律の制定及び改正は、その時々の国民意識の反映でもあります。この市民フォーラムで、少しでも動物愛護法の改正に向けて一般市民の意識が高まり、機運醸成につながることを願います。」 HSIの研究・毒性学部門のシニアディレクターのトロイ・サイドルは次のように述べている。「ヨーロッパから中国まで、動物愛護法が最初に制定された時期から、世界各国の動物福祉の規制には大きな進展がありました。日本の当局も動物福祉学を根幹としたグローバルなベストプラクティスの方向性に舵を切ることを期待し、特に、生命科学における実験動物の使用の削減、そして最終的には代替に力をいれてくださることを願います。」 以上 問い合わせ: HSI (日本): 山﨑佐季子, syamazaki@humaneworld.org (日本語・英語対応可) 動物との共生を考える連絡会: 青木貢一 info.dokyoren@gmail.com
新たな報告書が、日本の農薬の要件における1年間のイヌの試験の 省略を支持
東京 – ヒューメイン・ソサイエティー・インターナショナル(Humane Society International, HSI)は、長きにわたり日本の農薬規制において要件となっているビーグル犬を用いた1年間の反復投与毒性試験を、特定の条件下で省略できる十分な根拠を示した、食品安全委員会の委託研究の報告書の結論を歓迎した。 食品安全委員会や農林水産省等の農薬の規制当局が報告書の提言を受け入れれば、疑問視されているこの動物実験の世界的廃止に一歩近づくことになる。この試験は、すでにアメリカ、欧州連合、インド、ブラジル、カナダ、オーストラリア及び中国において、一連の試験要件から廃止されている。 HSI研究毒性学部門のシニア・ディレクターのトロイ・サイドルは、次のように述べている。「長期間に及ぶ農薬の毒性試験において、無条件にイヌを用い続けることが非人道的かつ消費者の安全を守るためには不必要であることが、科学により明確に示されました。科学的なレビューを委託した食品安全委員会の洞察力を称賛するとともに、当局がこの報告書に記された提言の運用に向けて具体的に取り組むことを期待します。」1年間のイヌの試験について: この試験においては、1年にわたり、ビーグル犬の群に、カプセル状のものを経口で、または食餌に混ぜた状態で、農薬に用いる化学物質が毎日投与される。その後、臓器等への損傷を評価するために、イヌは殺処分され、解剖される。 今回の委託研究の報告書は、農薬評価書286剤を分析したものであり、95パーセント近くのケースにおいて、長期間のイヌの試験が、要件となっている他の試験の結果以上の、ヒトの安全量を判断するために必要な情報を貢献しないことが明らかなった。 農薬の新規の有効成分(農薬の効果がある毒性を持った成分)を一つ登録するために、日本やその他の国では最大10,000匹ものげっ歯類、魚類、鳥類、ウサギや犬が何件もの毒性試験のために使われている。これらの試験の多くは、二つ以上の動物種を用いたり、二つ以上の暴露経路(経口投与、吸入、経皮等)で実施する等重複しており、その科学的な価値が疑問視されている。 報告書においては、稀ではあるが、他の動物種よりもイヌにおける感受性が高い場合等を含む、長期間のイヌの試験の要件を残すべき条件についても提言されている。 研究番号1501の「農薬の毒性評価における「毒性プロファイル」と「毒性発現量」の種差を考慮した毒性試験の新たな段階的評価手法の提言―イヌ慢性毒性試験とマウス発がん性試験の必要性について―」の報告書は、下記のリンクから閲覧できる。 https://www.fsc.go.jp/fsciis/technicalResearch/show/cho99920161501 問い合わせ:英語対応: キャサリン・ウィレット博士, kwillett@humaneworld.org 日本語対応: 山﨑佐季子, syamazaki@humaneworld.org ヒューメイン・ソサイエティー・インターナショナル(Humane Society International, HSI) 及びそのパートナー団体は、世界最大級の動物保護団体です。HSI は 25 年以上にわたり、科学、アドボカシ―、教育及び実践プログラムを通して全ての動物の保護に取り組んできました。「世界中の動物に畏敬の念を示し、動物虐待に立ち向かう」ウェブサイ ト― hsi.org
ラッシュのシャンプーバー、ヒューメイン・ソサイエティー・インターナショナルのグローバルな#BeCrueltyFreeキャンペーンを支援するため、日本で販売開始
メディアのダウンロード 動物実験をしない化粧品会社の株式会社ラッシュジャパン(以下ラッシュジャパン)が、ラッシュの固形のシャンプーバーの中で、世界的に最も売れている「ニュー シャンプーバー(レッドペッパー)」をリニューアルし、販売する形で、化粧品の動物実験と動物実験された化粧品の商取引を禁止するためにヒューメイン・ソサイエティー・インターナショナル(Humane Society International, 以下HSI )が展開するグローバルキャンペーンに参加することになった。リニューアルされるこのシャンプーバーには、HSI の#BeCrueltyFree (思いやりのある美しさキャンペーン)のメッセージが、世界中のSNS で最も使用されている言語のトップ2 である、英語と中国語で施されており、www.endanimaltesting.org からHSI のキャンペーンの誓約に署名をしてもらうことが狙いである。消費者の声は、各国で法規制を進めるために欠かせないものである。このシャンプーバーは、すでに今年初めにヨーロッパや北米で販売が開始されている。 残酷な化粧品の動物実験を禁止することを各国の政府に呼びかけるために、世界中ですでに100 万人の人々が#BeCrueltyFree のキャンペーンに賛同し、署名している。HSI やその他の団体のロビー活動や対消費者キャンペーンの圧力もあり、現在36 の国や地域が化粧品の動物実験の実施と新たに動物実験された化粧品の販売の禁止、またはそのいずれかの禁止を実現する規制を導入している。これらの規制が実現している国や地域には、欧州連合(EU )、イスラエル、インド、ニュージーランド、韓国、台湾やスイス等が挙げられる。 HSI の#BeCrueltyFree キャンペーンのグローバルディレクターのクレア・マンスフィールドは、次のように述べている。「HSI の#BeCrueltyFree キャンペーンは、ラッシュのご支援を大変光栄に思っており、2017 年をこのようなコラボレーションで始められることを嬉しく思っています。すでに世界各国で17 億人の消費者が、動物実験が禁止されている化粧品市場で生活しており、この#BeCrueltyFree の動きは広がり続けています。ラッシュのリニューアルされた新たなシャンプーバーは、我々の#BeCrueltyFree のメッセージをさらに多くの消費者に届け、世界中で未来永劫、残酷な化粧品の動物実験に終止符を打つことの手助けとなってくれます。このコラボレーションにより、日本においても化粧品の動物実験の禁止につなげることができればと期待しています。」 ラッシュの企業としてのエシカルな取り組みにおけるディレクターであるヒラリー・ジョーンズは次のようにコメントしている。「全世界が、動物実験からより現代的な動物を用いない安全性試験に切り替わらないと、動物たちは化粧品の動物実験の恐怖から逃れることができません。この醜い習慣に終止符を打たない限り、我々を真の美しさのための業界と呼ぶことはできません。その日までメッセージを皆で拡散し続ける必要があり、HSI のグローバルな#BeCrueltyFree の手助けができることを光栄に思います。」 ラッシュの「ニューシャンプーバー」は、頭皮を活性化させるためのシナモン、クローブやペパーミントなどのフレッシュな原材料を使った固形シャンプーである。シナモンの葉や、月桂樹とクローブの花芽のエッセンシャルオイルにペパーミントを加えた調合は、血流を良くし、毛包に刺激を与えることができる。イラクサとペパーミントを煎じたものを使うことにより、頭皮を活性化させ、健康的な髪の毛を促進する。また、ローズマリーは、頭皮の状態を整え、髪の毛に美しい輝きを与える。 @LushLtd @HSIGlobal #BeCrueltyFree 問い合わせ: ラッシュジャパン: 小山大作, lush-pr@lush.co.jp HSI ( 日本): 山﨑佐季子
Help us end animal cruelty
Start saving lives today by making a one-time gift—or protect animals worldwide all year long with a monthly contribution.
